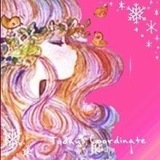まな板の正しい使用方法を知っていますか?
家庭に1つは必ずある「まな板」。
みなさんは、まな板は包丁を使うための
ただの下敷きだと思っていませんか?
実は、いい包丁を使っていても、
まな板次第で切れ味が悪くなってしまうこともあります。
また、まな板は正しいお手入れを行わないと
目に見えない雑菌がたくさん繁殖し、不衛生になります。
もっとひどくなると
食中毒にもなってしまうことも・・・
じゃあ、何を使ったらいいの?!と思うかもしれませんが
プラスチック製や木製のまな板には
どちらもメリット・デメリットがあるんです。
そこで、今回はそれぞれの種類のまな板の
メリット・デメリット
そして正しい使い方からお手入れ方法までご紹介します☆

プラスチック製のまな板
プラスチック製のまな板はデザインやサイズも豊富ですよね☆
お手入れが楽なことから、プラスチック製のまな板を
使用しているご家庭が多いのではないでしょうか?
しかし、プラスチック製も
メリット・デメリットがあるんですよ\(◎o◎)/!
■メリット
・お手入れが楽
・材質が硬いため、傷がつきにくい
・肉や魚の臭いがつきにくい
■デメリット
・手への負担が大きい
・滑りやすいので、安定感と安全性が低い
・寿命が短い 約2年
■正しい使い方とお手入れ方法
①使用する前に水にぬらす
使用前に水に濡らすことで、まな板のコーティング効果があるためといわれています。食材のアクや、生魚や生肉の脂分がまな板へ染み込みにくくなるのだそうです。
②汚れや食べカスを取るときは「除菌スプレー」を使う
プラスチック製のまな板を漂白する時って、
漂白剤を水に薄めて漬け置きする方が多いと思いますが、
実はスプレータイプの漂白剤のほうが除菌効果が高いんです!
集中的に使うところに直接吹きかけ、除菌しましょう!
2~5分ほど放置し、その後はよく洗い流しましょう。
③使用後は洗剤で洗い立てて乾燥させる
プラスチック製のまな板は汚れが落ちやすいので、
その日の汚れはその日に洗剤でキレイに落としてしまいましょう。
洗剤でキレイに落ちやすいところが、プラスチック製のいいとこですね♫
洗った後は、ペーパータオルで軽く拭き、立てて乾燥させましょう!
木製のまな板
木製のまな板といえば、料亭!って感じですよね☆
自分の家で使うには
手入れが難しそうで使いにくいんじゃないかと思っている方もいるでしょう。
でも、木製はプラスチック製にはないメリットがあるんですよ♫
■メリット
・柔らかいので包丁の刃が傷みにくい
・木製は手への負担を少なくしてくれる
・包丁の刃当たりが柔らかい
・すべりにくい為、安定感と安全性がある
・寿命が長い 約6~7年
■デメリット
・柔らかいためキズがつきやすい
・キズに雑菌が繁殖しやすい
・持ちを良くするには入念な手入れが必要になってくる
■*正しい使い方とお手入れ方法*
①木製のまな板も使用する前に水に濡らす
食材を切る前に必ず水でサッと湿らせると、食材がまな板にくっつき切りやすくなる上臭いや色もプラスチック製より付きにくくなるのだ。
②肉や魚を切るときは牛乳パックを使う
木製のまな板で魚や肉を切るときは、
見開きに切った「牛乳パック」を敷いて切ると、
まな板のキズつき・食材のニオイ移りを防ぐことができます。
食中毒の原因となる悪玉菌は
肉や魚に含まれるたんぱく質が大好物なので
直接まな板で切るのは避けた方がいいでしょう。
③使った後は洗って風通しの良い所で乾燥させる
木製のまな板は、洗った水を吸収し
重たくなるためカビや変色が起こりやすくなります。
使用後は、立てて乾燥させることによって
カビや変色を予防することができ長く使うことができます。
できれば洗った後、立てる前に
軽くペータータオルで拭くと乾きも早くなりますよ★
※直射日光があたる所で乾燥させると
割れたり反れたりする原因になるのでやめましょう。
④黒カビが生えてきたら「まな板用のヤスリ」を使おう!
黒カビが生えてきた場合、木製のまな板は
洗剤で落ちにくいため、まな板専用のヤスリで削ると
キレイな木のまな板に戻ります♫
ここで、注意してほしいのが
除菌したいからといって漂白剤につけるのはNGです!
木製は吸収しやすいため
漂白剤を洗い流しても中に残ってしまうんです。
除菌したい場合は、
除菌スプレーをかけたり、片面5秒ずつ両面に熱湯をかけて除菌しましょう♫
自分のスタイルに合った「まな板」をチョイスしよう♫
まな板の使用方法、お手入れ方法いかがでしたか?
まな板は、同じ場所ばかり使っていると
傷が集中的につき
その傷に細菌が染み込み繁殖していきます。
また、同じ面ばかり使っていると
雑菌や汚れが混ざってしまうので
表は野菜、裏は肉や魚と
使い分けるのも一つの方法です。
種類別にまな板を用意するのもいいでしょう♫
まな板は、自分の切りやすいものを使うのが一番なので
正しい使い方とお手入れ方法をマスターして
清潔を保ち、長く持つようにしていきましょう♫